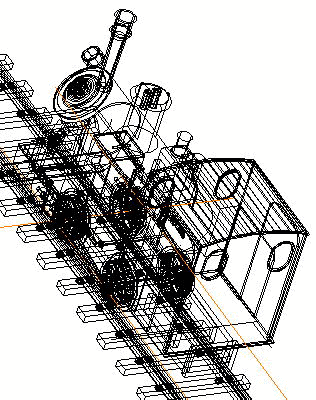
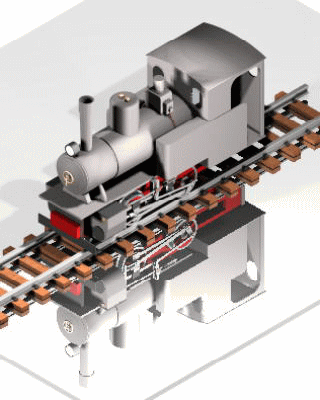
平成15年7月
4月の二俣線開通式以来しばらくでしたが、そろそろコッペルの製作に取り掛からなければなりません。 浜松駅近くの模型店アールクラフトで相談したところ、昨今は自作派のホビーストは激減して久しくO-Narrowは車両もディオラマも部品の入手は難しいとのこと。 と言いつつ、店主が引き出しの奥から、軽便用の動輪を探し出してくれました。 直径が13.5mmでコッペルの11.5φより大きいが、初心者には左右絶縁動輪の製作は難しそうで、これと小型モータを併せて購入しました。 但し、ウォームギアは特殊で、これは自作しなければなりません。 奥山線の写真資料を見るとコッペルは少なくとも3型式あったようで、それぞれの特徴を組み合わせてCADで描画してみました。 動輪が大きいためにやや足長のプロフィールになっています。
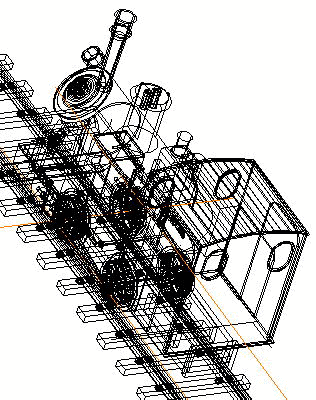
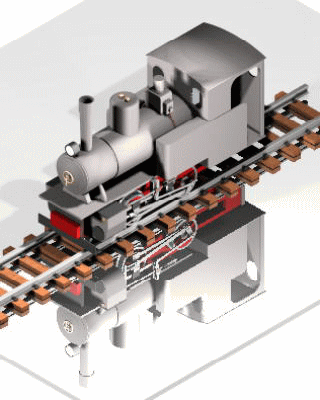
動輪セットには「なんさつ用」とラベルがついていました。 ウォームギアは剣バイトでねじ切りした後、折れた金鋸で作ったバイトで仕上げます。 穴あけと切断は慎重に。


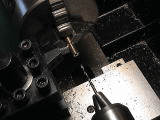
2003年8月
夏休み中の完成をめざして、これまでCADで設計しておいた図面に従って製作にかかりました。 シャーシや駆動系は比較的簡単に出来上がりましたが、キャビンやタンク周りのリベット打ち出しに難渋しました。 写真のような打ち出し治具を作って何度か試しましたが、これに手間取ると夏休み中に完成はおぼつかないと見て、今回はパスしました。 このゲージでリベットを省略すると、やはり写真のようにノッペリとした外観になってしまいます。 その他にも細部の手抜きをしましたが、休暇中に完成させることはできず、最も難しそうな、足周りのメカニズムを残すことになってしまいました。 鉄道模型趣味という雑誌や各種製作手引き書などは大変参考になりました。
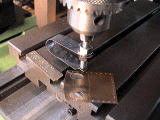
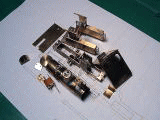
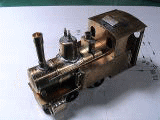
2003年9月
案の定、比較的シンプルなワルシャート式も足回りのクランク、バルブ機構でてこずりました。 前後の動輪は平ギアでリンクしてもスムーズに回転させるは精密な調整が必要です。
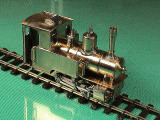
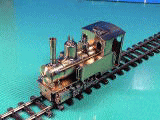
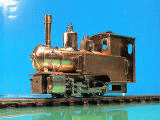
これまでは一般的な軌道給電をするつもりでしたが、試験的に屋外に放置しておいた線路の錆び、汚れがひどく、庭園鉄道のシステムを大変更しなければならないようです。 最近は2次電池の性能も向上してきたので、先頭の機関車はダミーで、後続の有蓋車をラジオコントロールのバッテリ駆動車にすることを検討中です。そうなると、折角、苦労して製作したコッペルですが、もっと軽量化して牽引負荷を小さくしなければなりません。 ただし、先頭車両にはビデオカメラを搭載することが可能になります。
平成15年10月 5インチ電動車の製作
ライブスティームは準備、給水、給炭、かたずけが大変なので、電動車を製作しました。モデルニクスから購入した吊り掛けモータ2基で前後の台車を駆動します。 走行抵抗軽減のため前輪と駆動後輪の荷重を3対7とする偏心台車にしました。 これで台車の前輪がSLの先輪のように駆動後輪を誘導して急曲線での走行抵抗を軽減しようという試みです。 なお4輪の荷重バランスをとるための軸バネやイコライザを省略したので、台車の左右のフレーム間の接合を柔構造にしています。 バッテリは軽自動車用を2ヶ直列にして前方に配置しました。 2段減速ギアーをいれたので牽引力はさすがです。 この電動車の前に種々ダミーの機関車を連結する予定ですが、エンジンや制御部がなく軽量なので色々趣向が凝らせそうです。 電池箱後ろの腰掛はシートが未装着です。

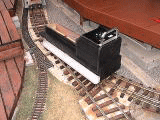

2003年12月
Oナロー16.5mmの奥山線もバッテリ駆動が必須となりましたがダミーコッペルにビデオカメラを搭載する目途が立たないので取敢えず客車を製作します。年末の連休を利用してCADでデザインしておいたサハ1101をレンダリングしてプロフィールを確認し製作に取り掛かります。 奥山線の客車はボギー台車による軽便らしからぬスマートな車体で全長が無骨なコッペルの2倍もあります。 連結器も近代的なナックル型ですが、オープンデッキだけが軽便の雰囲気をだしています。
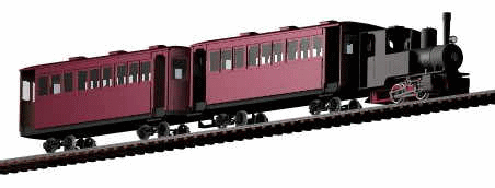
平成15年大晦日
塗装に自信がないので厚手のアート紙にCADの図面を印刷しカッターで切り抜ぬいてボール紙と木材で補強しました。 両面テープと瞬間接着剤は手軽で確実に接合できるので手先が不器用な者には大変重宝します。 例によって細部は省略しましたが写真のように床下、車内ベンチ、屋根のベンチレータと塗装などは年内に完成させることができませんでした。 2台目はバッテリを搭載するため後ろ半分が貨物用の貨客車、ハニとなります。 今度はこれまでの数々の失敗経験を生かせそうです。 年末までに積み上がった未読の書籍があるので以後の製作は2月以降になりそうです。


